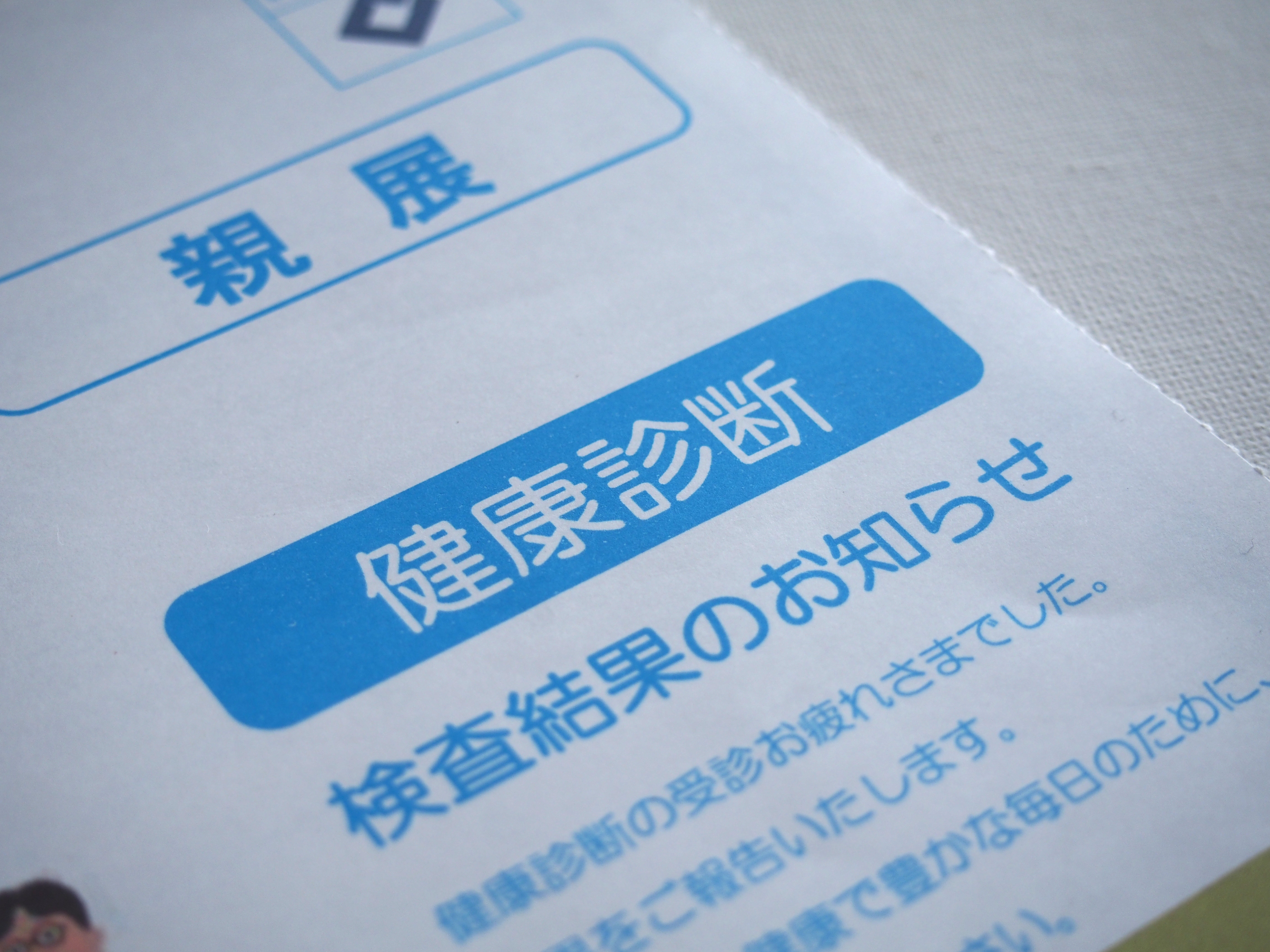- コラムタイトル
-
確定申告、本当に不要? 会社員でも申告すべき場合の条件とは
- リード
-
「会社員だから確定申告は不要」と思っていませんか?たしかに多くの会社員は、年末調整だけで税金の計算が完了します。しかし副業や住宅ローン控除、医療費控除など、特定条件に当てはまる場合は、確定申告が必要です。本コラムでは、会社員でも確定申告が避けられないケースを具体的に解説し、スムーズな申告のポイントを紹介します。
- コラムサマリ
この記事は約5分で読めます。
1.会社員でも確定申告が必要なケース
2.確定申告を活用すれば税金が還付される可能性があるケース
3.確定申告をスムーズに行うためのポイント
- 本文
-
会社員でも確定申告が必要なケースとは?
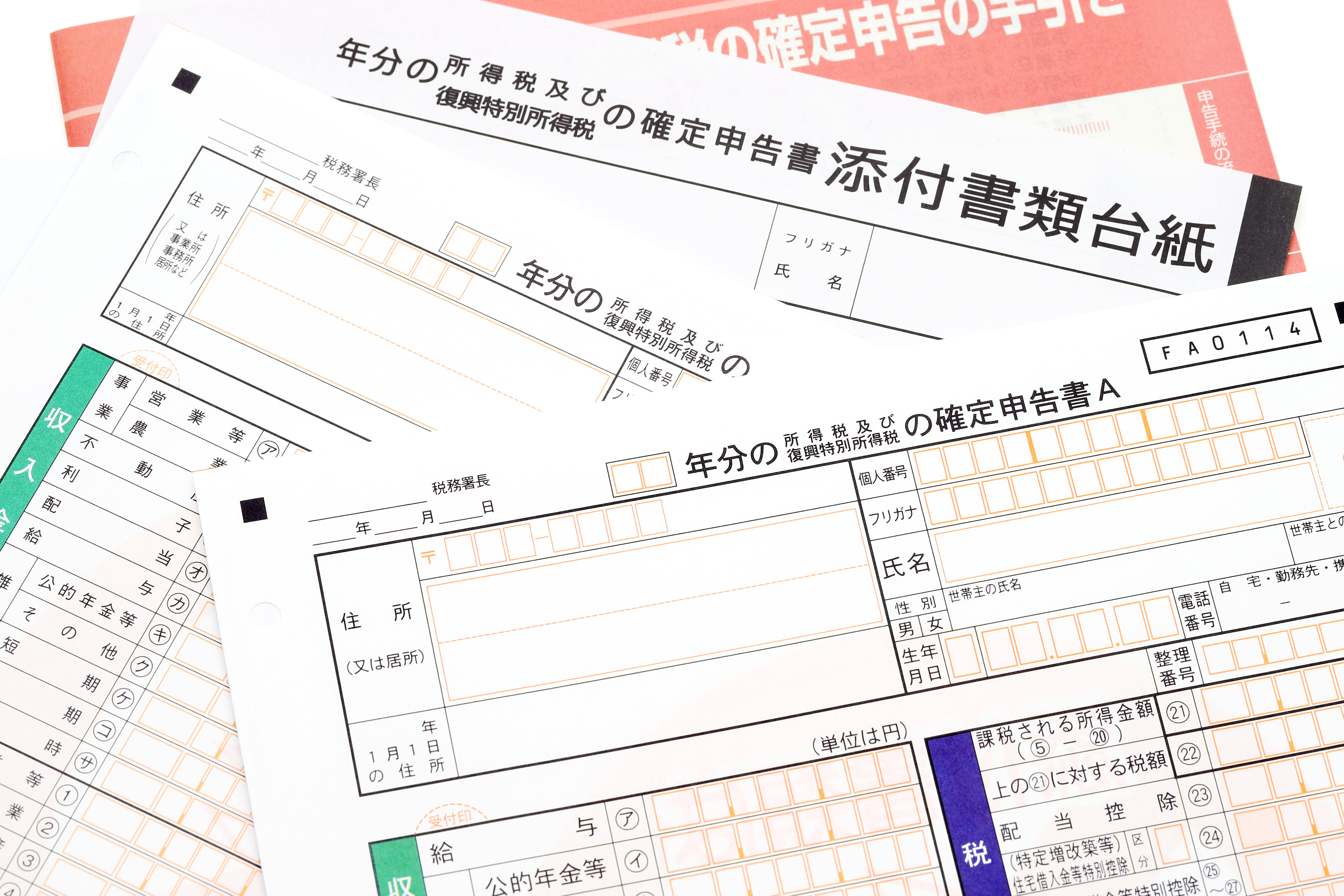
会社員であっても一部のケースでは、確定申告が必要です。ここでは、会社員でも確定申告を行わなければならない代表的なケースを紹介します。
年収が2,000万円を超える場合
会社員であっても年間の給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり、自分で確定申告を行わなくてはなりません。給与所得控除が適用されるため、収入のすべてに課税されるわけではありませんが、適正な申告をしましょう。
副業の所得が20万円を超えた場合
給与所得者の場合、副業の所得(所得=収入-経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。近年は 多様な働き方が広がり、副業 を行う人 も増えています。クライアントから支払調書を受け取る場合は、それをもとに正確な申告を行いましょう。
【対象となる収入の例】
副業による収入は、その性質や形態によって、いくつかの種類に分けられます。以下に、代表的な例を挙げます。
インターネットを利用した収入
・YouTubeなどの動画配信プラットフォームでの広告収入
・ブログ、SNSなどでのアフィリエイト収入
・オンラインマーケットプレイス、フリマアプリなどでの物品販売収入(継続的に商品を仕入れて販売している場合)
専門スキル・知識に基づく収入
・デザイン、ライティング、プログラミングなどの業務委託報酬
・コンサルティング、セミナー講師などの報酬
金融商品・資産運用による収入
・株式投資、暗号資産(仮想通貨)取引による譲渡所得・利益
株式投資や暗号資産(仮想通貨)取引による利益(年間所得20万円超)がある場合も確定申告の対象です。特に暗号資産の売却益は、雑所得として扱われ総合課税されるため、税額が大きくなる可能性があります。なお株式の場合、特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則確定申告は不要ですが、損失を翌年以降に繰り越したい場合や還付を受けるためには確定申告が必要になります。
ワンストップ特例を使わずにふるさと納税を行った場合
ワンストップ特例の申請書を期限内に提出しなかった場合や6 ヶ所以上の自治体へ寄付を行った場合は、確定申告が必要になります。ワンストップ特例制度を利用する場合でも、申請書の提出を忘れると確定申告が必要になるため、注意しましょう。
確定申告を活用すれば税金が還付される可能性があるケース

確定申告には、税金の支払いだけでなく適用できる控除を活用することで税負担を軽減するメリットもあります。ここでは、確定申告を行うことで得をする代表的なケースについて解説します。
住宅ローン控除を受ける初年度
住宅ローンで条件を満たすマイホームを購入し、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたい場合は、確定申告が必要です。なお確定申告は、最初の1回(購入年度の翌年の2月16日~3月15日まで)のみとなります。住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高に応じて一定金額が所得税から控除される制度です。
2年目以降は、年末調整で適用できますが、初年度に申請しなければ控除を受けることができません。
医療費が年間10万円を超えた場合
医療費控除を活用することで、年間にかかった医療費の一部を所得控除として計上できます。なお控除を受けるためには、以下の条件のどちらかを満たしていることが必要です。
・年間の医療費が10万円
・総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%を超えている
医療費控除のポイントを整理しましたので、自身が医療費控除を受けられるか確認してみましょう。
1.家族全員の医療費を合算できる
本人だけでなく扶養している家族の医療費も合算して申告ができます。
2.通院費や薬代も対象になる
病院への通院費や処方薬、治療のための特定施術(歯科矯正やレーシック手術など)も控除の対象になります。
3.高額療養費制度との違いを理解する
高額療養費制度は、健康保険の給付制度のため、確定申告とは別の手続きが必要です。ただし高額療養費制度で補てんされない部分は、医療費控除の対象となります。
このように医療費控除を適用することで、所得税の還付を受けられる場合があります。医療関連で大きな出費が発生した年は、確定申告を検討しましょう。
確定申告をスムーズに行うためのポイント
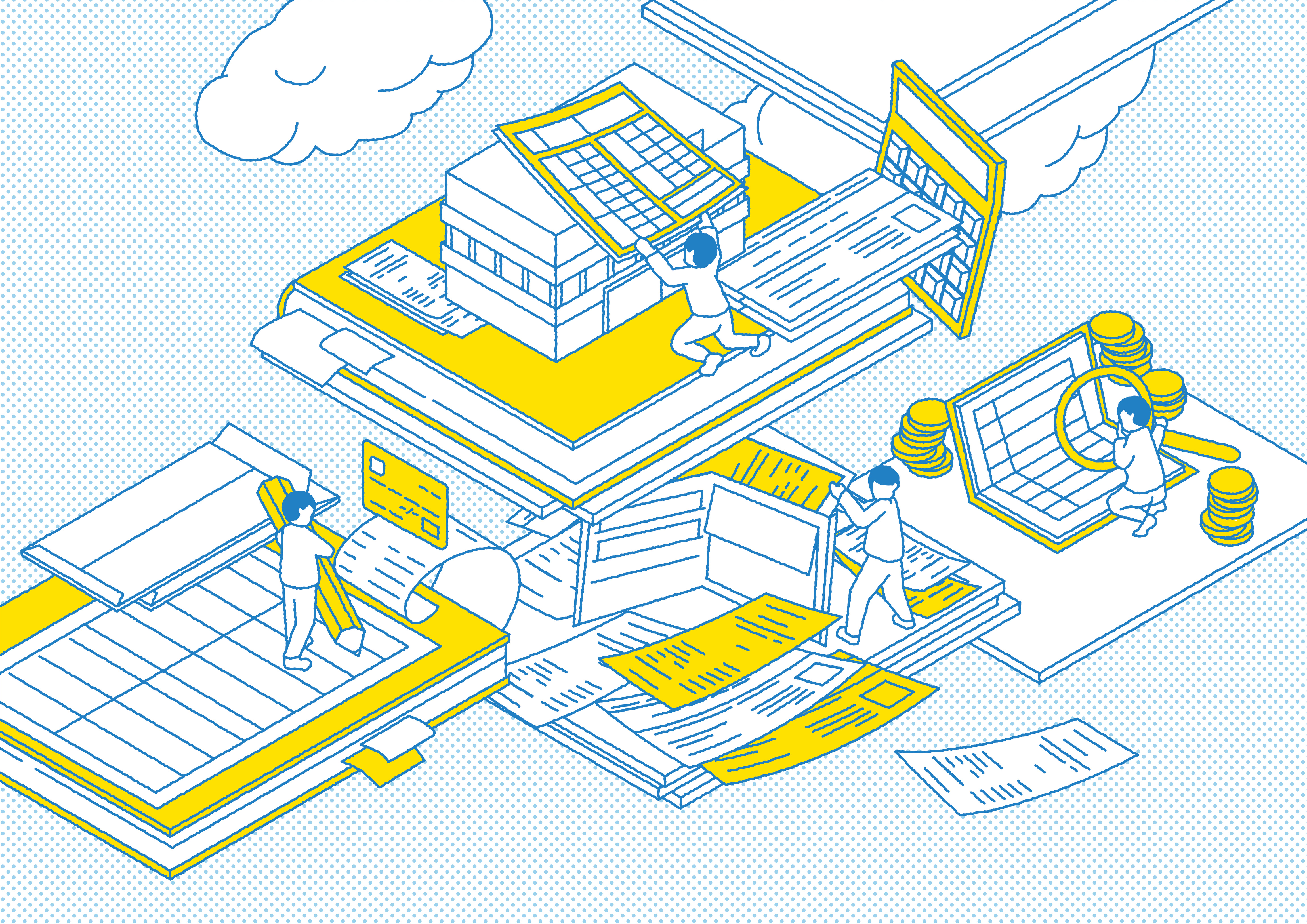
確定申告は、手間がかかると思われがちです。しかし適切な準備をしておけば問題なく進めることができます。ここでは、事前に準備しておくべきポイントや確定申告を簡単に行うための方法について解説します。
必要な書類を早めに準備しよう
確定申告をする際は、内容によってさまざまな書類が必要です。しかし事前に用意しておけばスムーズに確定申告書の作成ができます。必要になる可能性のある主な書類には、以下のようなものがあります。
・源泉徴収票
・支払調書
・医療費の領収書(医療費控除の申告)
・寄附金の受領書(ふるさと納税の申告)
・住宅ローンの年末残高等証明書(住宅ローン控除)
・土地建物の登記事項証明書(住宅ローン控除)
・土地建物の売買契約書の写し(住宅ローン控除)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど) など
自分が申告する内容を確認して早めに必要書類を準備しておきましょう。
e-Taxを活用して効率的に申告
確定申告の手続きは、税務署に直接出向く以外にもe-Tax(電子申告)を利用することでオンラインでの確定申告を完結できます。e-Taxの主なメリットは、以下の5点です。
1.自宅で手続きができる
税務署に行かなくてもインターネットを使える環境であれば自宅で確定申告を完了できます。「平日の日中は仕事が忙しい」「税務署が遠くていけない」という人にとってはとても便利です。
2.土日祝日でも申告できる
e-Taxであれば土日祝日でも申告できます。紙の申告書類を税務署へ郵送する場合、基本的に土日祝日は郵便局が営業していないので平日提出(簡易書留など追跡できるものがおすすめ)することが必要です。
3.還付金の処理が早い
e-Taxを利用すると紙の申告よりも還付金の処理が早く行われるため、払い過ぎた税金がある場合、早めに受け取ることができます。
4.入力ミスの防止
e-Taxの場合、自動計算機能があるため、計算ミスを防ぐことができます。また必要情報を入力するだけで申告書を作れるため、初心者でも使いやすいです。
5.マイナンバーカードと連携可能
マイナンバーカードを利用すると、ログインや本人確認がスムーズになり、電子証明書を活用して簡単に申告手続きを完了できます。e-Taxを活用することで確定申告の手間を軽減し効率的に税務処理を進められるため、利用を検討してみましょう。
まとめ
確定申告が必要なケースを把握し、適切に対応することで税制上のメリットを享受できます。本コラムのポイントを整理したうえでスムーズな確定申告のために押さえておくべきことを確認しましょう。会社員で年末調整を行っている場合でも、確定申告をしたほうが税金の還付を受けられる可能性があります。自分に該当するケースがないかを確認し、早めに準備を進めましょう。
この記事の執筆協力
- 執筆者名
-
藤森みすず
- 執筆者プロフィール
-
食品衛生管理者、情報処理のアプリケーションエンジニア。21年ほどメーカー系SIerにてプログラマー、システムエンジニアを経験。退職後、Webライターとして様々な分野の執筆を行う。一時期、飲食業開業について学んだことがあり、起業関連の情報にも精通。FXなど投資関連も得意とする。
- 募集文書管理番号